 悩んでいるママ
悩んでいるママ子供たちだけでお留守番させるのが本当に不安だわ…
こういった悩みを持たれているパパやママ、おじいちゃんおばあちゃんも多いのではないでしょうか。
お留守番するのは家の中とはいえ、病気・怪我・犯罪に巻き込まれてしまう可能性もゼロではありません。
共働きの家庭の方などは、子供たちだけで留守番をさせている不安から仕事に集中できない事もあるでしょう。
そこで、この記事では子供たちだけでお留守番をする場合に、保護者が抱く不安をできる限り取り除くための対策を解説していきます。
- 子供のお留守番事情がわかる
- 子供に留守番をさせる時の不安
- 子供だけでのお留守番で起こる不安の解決策
子供のお留守番事情
現代の日本における、子供たちのお留守番事情はどうなっているかご存知ですか?
私自身子供がまだ小さいため子供たちだけでお留守番をさせるという事は考えたこともありませんが、気になっていました。
セコム株式会社は、乳幼児から小学生の子供の保護者147名を対象に「子どもの安全対策に関する調査(2020)」を実施しています。
子供のお留守番に関する調査結果の概要は以下の通りでした。
- 週に1回以上子どもだけで留守番をさせている家庭は、小学校中学年以上で6割
- 子どもの留守番に際し「来訪者があった際の対応」「火の使用」についての約束ごとが上位
子供に1人で留守番をさせている家庭は、小学校中学年以上で約6割
調査結果を見ると、小学生低学年から徐々に1人でお留守番をすると頻度が増えてきています。
週に1回以上のお留守番をする頻度は、小学校低学年で約35%、中学年で59%、高学年で65%となっていて、半分以上の家庭では小学生だけでお留守番をさせている事がわかります。



小学生の子供たちが1人でお留守番をしているのに驚きました。でも夫婦で働いている家庭も多いですし、そうせざるを得ない状況なんですよね。
子どもの留守番に際し「来訪者があった際の対応」「火の使用」についての約束ごとが上位
「子供の留守番に際し、約束している事はありますか?」の質問に対する回答は以下の通りです。
- 誰かが訪ねてきてもドアは開けない(78%)
- 玄関や窓の鍵は施錠したままにする(68%)
- インターホンが鳴っても応答しない(67%)
- あらかじめ決めた電話以外には出ない(33%)
- 火を使わない(69%)
- ベランダに出ない(35%)
- その他(9%)
- 浴室に入らない
- キッチンに入らない
- 家の庭に出ない
- 携帯電話の電源を入れておくホームセキュリティーを警戒状態にしておく
- 何かあれば電話する、ホームセキュリティーの非常ボタンを押す
- 子どもしかいないことがわからないように静かにする
- 調理をする際は、レンジとトースターのみの使用にする
- 特にない(7%)
子供だけで留守番をする際の約束事を決めている家庭が9割以上となっています。
特に多かった回答は「誰かが訪ねてきてもドアは開けない」「玄関や窓の鍵は施錠したままにする」「インターホンが鳴っても応答しない」「火を使わない」が6割以上の方で回答されています。
「来訪者への対応」と「火の使い方」の2つに関する決め事を行なっている家庭が多いということですね。



私が小さい頃も同じように親と約束事を決めてお留守番をしていた記憶があります。その辺は、今も昔も大きく変わっていないようですね。
子供だけでお留守番をする時に感じる不安
小学生のうち6割以上の子どもたちがお留守番をしているという状況がわかりました。
子供たちだけでお留守番をさせたくないのが本心ではあると思いますが、どうしてもせざるを得ない状況もあるはずです。
そのような中で、子供だけでお留守番をするときにどのような事に不安を感じるのでしょうか。
アルソック株式会社が、小学生の子どもがいる共働き家庭の男女500人に対して「小学生のお留守番実態調査」を実施しています。
子供だけでのお留守番に不安はある?
「子供だけでお留守番をさせる事に不安はあるか」の質問に84.6%の方が「不安がある」「どちらかといえば不安がある」と回答しており、何かしらの不安を抱えたまま子供たちにお留守番をさせている事がわかります。
不安を感じる人が多いという事はそれだけ物騒な事件や事故などのニュースを目にする機会が増えたからではないでしょうか。
子供だけのお留守番は、どんな事に不安を感じる?
子供だけでのお留守番が不安と感じた方にその内容を質問したところ、結果は次のようになりました。
| 訪問者対応 | 66.7% |
| 居空き(在宅中の侵入者) | 51.8% |
| 急な体調不良 | 51.8% |
| 地震などの災害発生 | 47.5% |
| 火遊びなどによる火災 | 45.6% |
| ゲームや動画の見過ぎ | 40.0% |
| 親が知らないうちに外出 | 36.4% |
| 電話対応 | 21.7% |
訪問者の対応への不安が66.7%、居空きに関する不安が51.8%、急な体調不良に関する不安が51.8%と上位を占めています。
これら3つの項目に関しては、子供たち側でコントロールする事は非常に難しいものです。
そのためしっかりと安全への対策を講じておく必要があります。



防犯対策をおろそかにしていると、子供たちが保護者との約束事を守っていたとしても事件や事後が起こってしまうのが怖いところです。
不安の解決策と防犯対策
ここからは、調査結果にあげられた不安に対する解決策と今から出来る防犯対策について解説していきます。
訪問者対応の不安に関する解決策
訪問者対応と聞くと、友人の訪室や郵便物の配達など一見すると危険な事は無いように感じてしまいますが、配達員や警察官などを装って侵入を図ろうとする者がいる事も事実です。
子供たちだけでなく、高齢の方もターゲットになりやすい事もあります。
こういったトラブルや犯罪に巻き込まれないようにするには、訪問者対応について親子で約束事を決めておくという事が有効です。
例えば、上記アンケードでも回答がありましたが次の3つが有効といえます。
- 誰かが訪ねて来てもドアを開けない
- インターホンに応答しない
- ドアや窓の鍵をかけておく
しかし、これだけでは訪問者としての対策はできても、侵入者の対策は不十分といえます。
インターホンに応答がないと家主が不在と思われ侵入を図られてしまう可能性もあるからです。
自宅に在宅している時に不審者が侵入する場合を居空きと呼び、子供たちが留守番している時に侵入されてしまうととても危険です。
次の項目で居空きに対する対策方法を解説していきます。
居空きに対する対策方法
居空きの侵入経路としては、ドアと窓の2箇所が多いと報告されているため重点的に侵入者対策をしていく必要があります。
居空きへの対策は次の2つが効果的です。
- 補助鍵や防犯フィルムを使用する
- ホームセキュリティーを導入する
補助鍵や防犯フィルムを利用する
窓についているクレセント錠とは別に補助鍵を付ける事で、鍵を開ける手間が増え簡単に突破されにくくなります。
都市防犯研究センターが報告している、鍵を開けるのに5分以上時間がかかると7割の侵入者が諦めるというデータを見ても有効な方法だと言えますね。
また、防犯フィルムを窓に貼り付ける事で、窓が割れにくくなるため補助鍵とあわせて使用することで侵入しにくい窓にすることができます。
ホームセキュリティーを導入する
補助鍵や防犯フィルムだけでは不安という方には、ホームセキュリティーの導入がオススメです。
ホームセキュリティー会社といえば、アルソックやセコムなどが有名ですね。
ホームセキュリティーを導入する大きなメリットは、24時間365日いつでも警備をしてくれる点です。
窓やドアの施錠を意識して行なっていても、人間たまには忘れてしまうことだってあります。
そういった時に、万が一居空きに入られてしまったらと考えるととても恐ろしいものです。
アルソックやセコムでは、家の中だけのセキュリティーのみならず、外出時のセキュリティー用品も取り扱っているので、学校や塾への通学やお出かけの時も安心して送り出すことができるのでオススメです。
急な体調不良や火遊びによる火災への対策
不審者の侵入の次に怖いのが、子供の急な病気や怪我、そして火遊びによる火災の発生です。
もし子供ひとりで留守番をしている時に、急な体調不良や火災が発生してしまった場合、子供たちはどうしたら良いかわからずパニックになることも考えられます。
小学生ぐらいの子供たちに、救急車の呼び方や消火器の使い方を教えるのはとても難しいですよね。
そういった場合にもホームセキュリティーを導入しておくことで、すぐさま警備会社へ通報をすることができるため万が一の事故を減らすことができます。
子供のお留守番をもっと安全に!
この記事では、現代の子供たちのお留守番事情やお留守番への不安とその解決策を解説してきました。
仕事や用事など子供たちだけでお留守番をしなければならない状況となる家庭も少なくありません。
特に、小学校にあがってから遅くまで預かってくれる施設がないという自治体も多い上に、核家族化により祖父母など面倒を見てくれる人が家にいないという家庭も増えて来ています。
こういった環境の中でも、子供たちの安全を守ることには率先して取り組んでいく必要があります。
この記事で紹介した「補助鍵や防犯フィルムの取り付け」「ホームセキュリティーの導入」は低予算で実施できる有効な防犯対策です。
万が一の事態が起こってしまってから後悔することのないように、しっかりと子供の防犯対策に取り組んでいきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
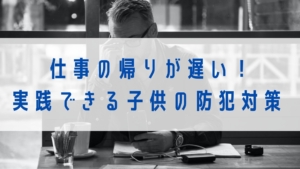
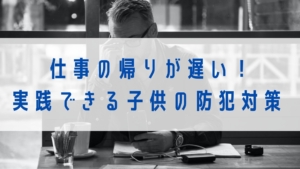
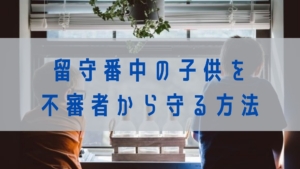
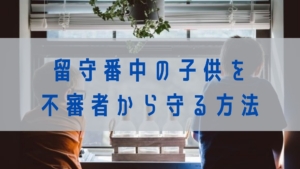

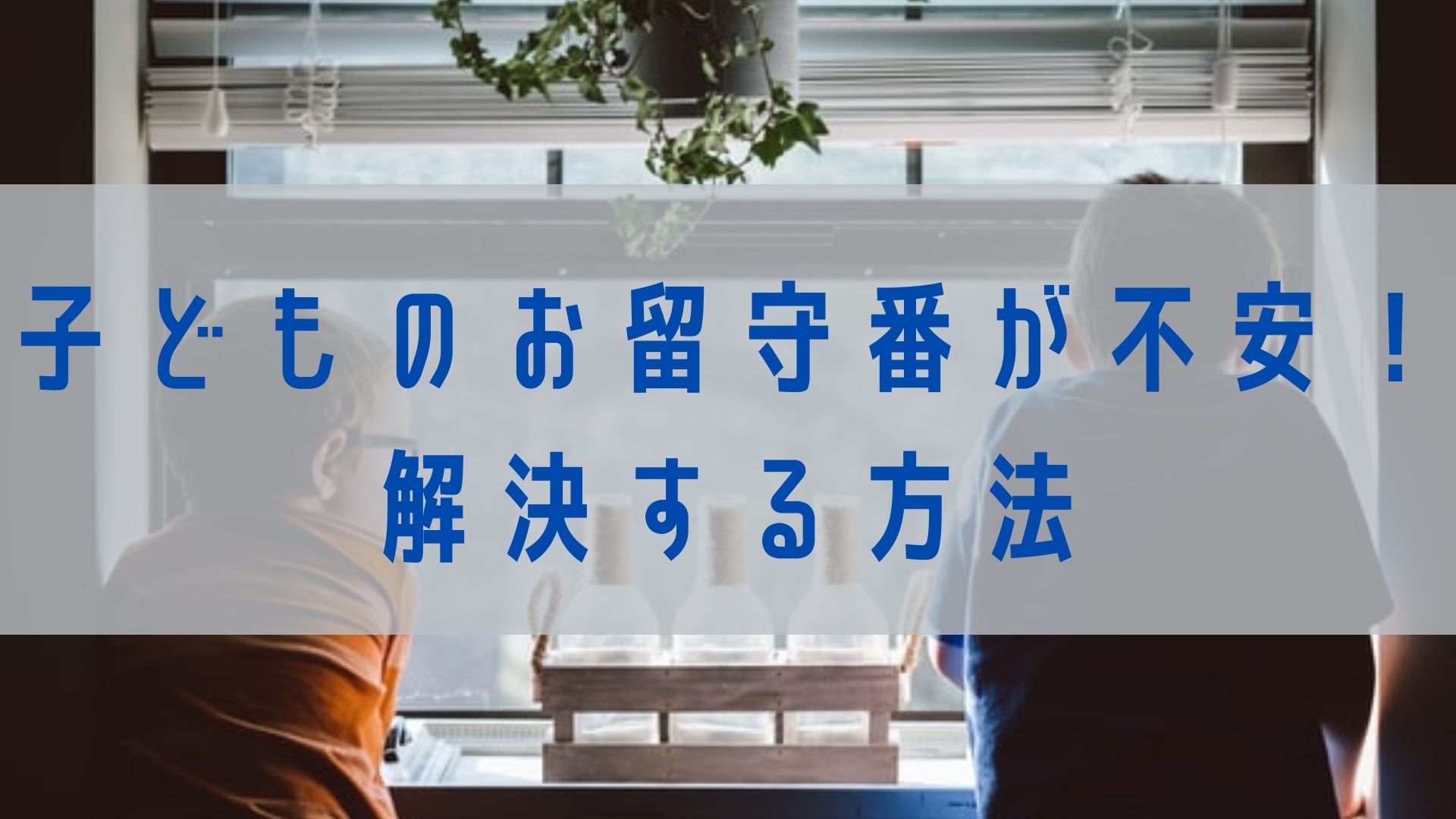
コメント